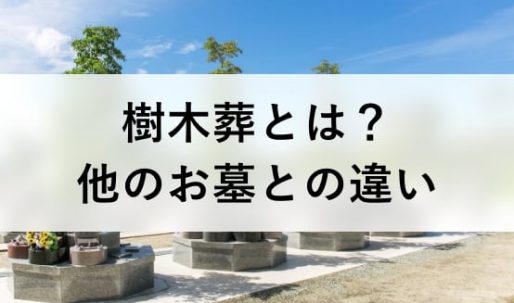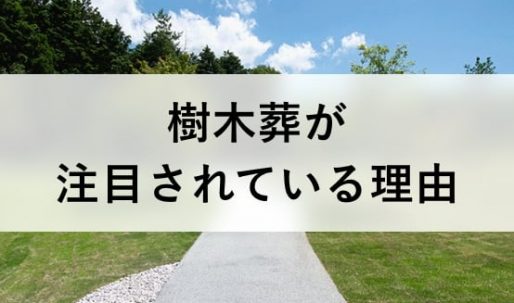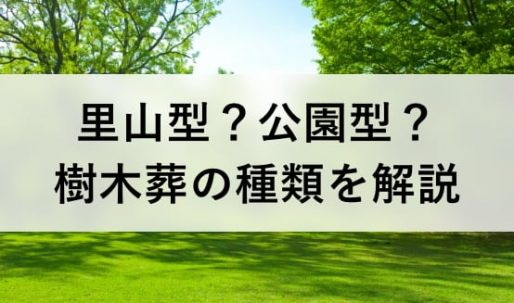2023.11.22
樹⽊葬が注⽬されている理由を社会背景から解説
この記事の目次はこちら!
ライフスタイルが多様化する中で、さまざまなタイプのお墓が選ばれています。そのうちのひとつで、昨今注目を集めているのが、花木を墓標とする樹木葬です。
この記事では、戦後から現代にいたるまでの社会の移り変わりと、お墓の変遷について解説しつつ、樹木葬がどのように始まり、どのように広まっていったのか、樹木葬がどうして注目を集めているのかを、深くご紹介いたします。
最後には、樹木葬の注意点についても言及しています。樹木葬に興味のある方、樹木葬を検討している方は、どうぞ最後まで読み進めてみて下さい。
樹木葬が普及するまで
まずは、樹木葬がどのような歴史をたどって普及していったのか、戦後日本のお墓の歩みとともに、解説いたします。
空前の霊園ブーム
戦後の日本を生きる私たちにとって、「お墓」と聞くと墓石を連想する人が大半ではないでしょうか。お寺の境内に立ち並ぶお墓は日本人の原風景のひとつであるとも言えます。また、高度成長期を経て国中が経済的に豊かになると、空前の建墓ブームが起き、日本各地に巨大霊園が造成されていきます。
戦後に霊園ブームが起こったのにはいくつかの理由が考えられます。
都市への移住・核家族化
生まれた土地にずっと住み続けるのであれば、先祖が守ってきたお墓に入ることができます。しかし、故郷を離れた人たちは新たな場所で家族を作るため、自らのお墓も新たに用意しなければなりません。
昭和の時代では、いまほど弔いのかたちは多様化しておらず、都市においても故郷と同じような墓石が求められました。こうした社会的なニーズを受けて、都市型の霊園が造成されていくこととなります。
戦後の日本は経済成長も著しく、地方から都市部への人口流入が急増します。戦後にニュータウンや公団住宅が生まれたのと同じように、「亡き人の家」であるお墓も、たくさんのお骨を受け入れられるだけの数が必要となりました。
旧来からある地域の共同墓地やお寺の境内墓地だけでは急激な需要増加に追い付かないことから、山や森を切り開いた巨大霊園が造成されていったのです。
経済成長と戦死者への追悼
墓石を建立するには多額な費用が必要で、誰もが簡単に建てられるものではありませんでした。しかし、日本が高度経済成長をなしとげ、一億総中流社会が実現することにより、多くの人たちが経済的に裕福になり、念願の墓石を建てられるようになったのです。
加えて戦後の日本の繁栄は、太平洋戦争で亡くなった方たちのもとに築き上げられました。家族や親戚を戦争で亡くしたという人も多く、戦死者への追悼や供養のためにお墓が建てられていったという側面もあります。
石材加工技術の向上と安価な外国材
どんなに需要が増えても、供給が追い付かないことにはブームは生まれません。石材業界側においても、人造ダイヤモンドの開発によって、切削機や研磨機などの加工用具が進化します。石材加工の技術が飛躍的に向上したことで、墓石の大量生産が可能となりました。
1990年代になると、国内だけでは原石の採石が追いつかず、韓国や中国などの外国の石材に頼るまでになります。また、外国の石材は国内産のものより安価なものが多く、より多くの方がお墓を建てる一因となりました。
樹木葬の登場とその遠因
1990年代、お墓を巡るさまざまな新しい動きが見られるようになります。
日本は少子高齢化社会に突入し、バブル経済の崩壊によって経済成長も停滞します。これらは、物理的にも経済的にも、子の世代が親世代を支え、弔うことの負担が増すことを意味します。世の中の大きな変化にあわせて、お墓のあり方も多様化を見せ始める中で、樹木葬が生まれます。
少子高齢化と承継問題
日本の人口構造は、かつては若い世代が高齢者をしっかりと支えることのできる社会でした。しかし、現代に近づくほどに若い人の割合はどんどん減少し、2030年には人口の3分の1近くが65歳以上の高齢者になるものと見られています。若い世代が高齢者を支えることそのものが大きな負担となり、それはお墓においても例外ではありません。
2022年の出生数は、過去最少の77万747人、合計特殊出生率は1.26ですから、子のない世帯や一人っ子世帯が多いことが分かります。
子のない世帯ではそもそもお墓の承継は困難です。また、一人っ子世帯でも女児しかいない場合、他家に嫁いでしまうことで実家のお墓を承継できなくなってしまいます。ライフスタイルが多様化しているというものの、日本のイエ制度による男系の単系承継(男性が家督を継ぐ)という考え方はいまでも根強くあります。
こうした事情を背景に、墓じまいが増え、承継の心配がないとされる樹木葬が注目を集めていくこととなります。
バブル経済の崩壊
バブル経済の崩壊後、日本は長きにわたる不景気に突入し、お墓の現場においても安価なものが求められるようになりました。
経済成長の時代は、お墓にお金をかけることが故人や先祖の供養となると考えていた人も少なくありませんが、バブル崩壊以降はその反動として「大切なのは心。手を合わせられるだけで充分」という考え方も受け入れられるようになります。
お金をかけないお墓のかたちとして、樹木葬や納骨堂が注目を浴びます。また、昨今では墓石においても、モダンでコンパクトなものが選ばれるようになりました。
弔いの個人化と多様化
現代は、個人の考えや多様性を大切にする社会です。伝統的な慣例に従うことよりも、自分自身の考えを優先すべきと考える人もあらわれるようになりました。
お墓や弔いに対しても同様で、個人の生き方が多様化するにつれてお墓のかたちもまた多様化しています。かつては墓石一択だったものが、いまでは、墓石、納骨堂、樹木葬、永代供養など、さまざまな選択肢の中から自分が望むお墓を選べるようになりました。
日本初の樹木葬は「里山型」
樹木葬は、もともとは「里山型」として産声を上げます。まずは里山型の樹木葬について解説します。
日本初の樹木葬ができるまで
岩手県一関市の祥雲寺の住職に赴任した千坂嵃峰(げんぽう)さんは、1991年に「葬送の自由をすすめるの会」が実施した散骨に危機感を感じ、その対案として樹木葬のアイデアを思いつきます。
また、お寺の郊外の荒れ地を購入し、檀家の若い人たちと間伐や草刈りを行った際に、荒れた自然に美しい風景がよみがえるのを目の当たりにし、人の手が加わることで里山がどんどん美しくなっていくことを体験したと話します。
こうして、新しい埋葬のかたちと、里山の環境保護というふたつのコンセプトを組み合わせた樹木葬のイメージが具体的に固まります。1995年に「北上川流域連携交流会」を発足させ、土地探しと、行政への墓地使用の許可申請を並行して行います。1999年8月にようやく里山を墓地とする認可が下り、そして同年の11月についに樹木葬墓地を開設します。
開設当初から地元新聞が大きく取り上げたことで、多くの反響が寄せられます。2000年4月には現地説明会を開催し、その後は毎月、首都圏での説明会を実施するまでに至ります。首都圏での動きは、やがて新聞、テレビ、雑誌などに取り上げられるきっかけとなり、こうして全国に樹木葬が知られるようになりました。
なお、現在は祥雲寺の子院である知勝院が樹木葬の管理を引き継いでいます。
知勝院の樹木葬の特徴
「里山型」の先駆けである知勝院の樹木葬の特徴は次の通りです。
- 骨壺を用いず、穴を掘って直接土の中に遺骨を埋葬する
- 墓石やカロートなどの石材やコンクリートを用いない
- 承継者が続けて使用できる。承継者がいない場合も永続的に改葬されずに保護される
- 同一の墓域に複数の人を埋葬できる。家族でなくても可
- 植樹する花木は地域の在来種の中から選ぶ。生態系を乱す外来種や園芸植物などの持ち込みはできない
- 火事防止のため線香、ローソクは使えない
- 生態系防止のため、お供え物を放置できない
- お参りは通年できるが、冬期間は積雪のため埋葬できない
- 宗旨宗派を問わない
まさに、旧来の方法に縛られない自由で新しい埋葬供養と、里山の保全という自然にやさしいお墓を実践した取り組みであることが分かると思います。
全国的に普及していく「公園型」
公園型とは、公園のように整備された都市部の霊園で展開される樹木葬のことです。現在全国的に普及している樹木葬は、里山型ではなく、この公園型と呼ばれるものです。
知勝院の樹木葬が世間に知れ渡ることによって、たくさんの寺院や霊園事業者もそれを参考に樹木葬に乗り出します。
しかし、すべての寺院や霊園が墓地利用できる山林を持っているわけではありません。そのため、既存の霊園の中で樹木葬区画を新設するところが増え、現在では、全国各地でさまざまなコンセプトの樹木葬墓地を見ることができます。
公園型樹木葬の特徴
公園型の特徴は、以下の4点に集約されます。
- 里山ではなく、都市型の霊園の中で行われる樹木葬
- 多くの樹木葬が、墓じまい不要で永代供養付き
- 宗旨宗派を問わない
- 樹木を墓標とするだけでなく、石のプレートやモニュメントを用いたものもある
都立小平霊園の樹木葬
公園型樹木葬の代表例が東京都立小平霊園です。横浜市に次いで、早い段階で樹木葬を採用しました。
東京都においても都民から「承継を前提としないお墓」「集合墓地」「自然に還りたいという志向」といった声が寄せられていました。それを受けて、知勝院を視察した上で新設されたのが、小平霊園の樹林墓地と樹木墓地です。
樹林墓地では、樹林の下に他の方の遺骨とともに共同埋葬するいわゆる「合祀」が行われます。一方で樹木墓地は、シンボルツリーの周囲に設けられた個別カロートの中に一体ずつ埋葬します。
エンディングセンターによる桜葬
自治体以外による樹木葬でよく知られるのが、認定NPO法人エンディングセンターが管理運営する「桜葬」です。
東京の桜葬は、町田市真光寺の「町田いずみ浄苑」に、大阪の桜葬は高槻市の神峰山寺の境内にあります。シンボルツリーを桜として、さまざまなデザインの個別埋葬、共同埋葬型の樹木葬プランが用意されています。
公園型が普及した理由
里山型ではなく、公園型が普及したのにはいくつか理由があります。
ひとつは、墓地供給側である霊園業者がすぐにとりかかれたからです。里山型であれば、行政から山林を墓地として使用するための認可を得なければならず、開設までに長い時間と膨大な手続きが必要です。
また、墓地開設後も、環境を維持し続けることが求められるため、人の手による地道な管理が必要です。一方で公園型は、これまで石塔だったお墓が花木に代わるだけなので、管理側にそこまで大きな負担がないことが考えられます。
そして、各地で樹木葬霊園ができると、消費者もそれに反応します。樹木葬という新しいコンセプトのお墓に心惹かれる人は少なくなく、これに加えて、「緑豊かな景観」「墓じまい不要」「永代供養付き」「宗派問わず」などの現代人のニーズに応える特徴によって、注目を集めます。
さらに、里山型であれば遠く離れた場所まで行かなければなりませんでしたが、都市の中で行われる公園型が普及することによって、樹木葬がより身近なものとなりました。
樹木葬が注目されている4つの理由
ここまで、戦後の日本社会において、どのように樹木葬が普及していったのかを時代の流れに沿ってご紹介してきました。
これらを踏まえて、ではどうして樹木葬が注目されるようになったのか、そのポイントを改めてまとめてみましょう。
キーワードは「脱承継」「宗教」「自然回帰」「石よりも花木」の4点ではないでしょうか。
脱承継(お墓を継がなくてよい)
核家族、少子高齢社会の現代の日本は、家族や先祖のつながりよりも個人の生き方が重視される風潮にあります。
継承墓は家族や先祖のつながりのシンボルそのものと言えるものでしたが、継承墓の承継は、自由に生きようとする人にとっては重荷と感じられることもあるようです。
樹木葬が打ち出したコンセプトのひとつが承継不要。万が一お参りの人がいなくなったあとも、樹木や区画はそのまま保護されるか、あるいは合祀に移してもらえます。
死後のお墓の承継について考えなくてよいことが、現代人の潜在的ニーズにマッチしたのです。
宗教不問(お寺に属さなくてよい)
継承墓は家族や先祖のつながりのシンボルとお伝えしましたが、亡き家族や先祖の供養を担うのが菩提寺です。つまり、継承墓を守り続けることは、菩提寺とのつながりをも維持することを意味します。
その一方で、ライフスタイルが多様化することで宗教観も多様化します。菩提寺による伝統的な供養の方法よりも、自分らしいお墓の在り方が求められるようになりました。
そのような時代にあって、宗教宗派を問わない樹木葬は、伝統的な慣例に縛られないお墓として注目を集めていくこととなります。
自然回帰(自然の循環に死後を託す)
樹木葬を選ぶ多くの人から聞かれる声に「自然の中で眠ることができる」「埋葬された死後の自分が、土となり、木の養分となれる」といったものが挙げられます。自分の死後が自然に還っていくことを志向する人が一定数いることが分かります。
仏教が説く伝統的な死後の物語(極楽浄土や輪廻転生)、あるいは日本古来から続く祖先とのつながり(氏神となって共に生きる祖霊)などはいまでも根強く私たちの中で信じられていますが、一方で「伝統よりも個人の自由が大事」と考える人たちにとって、これまでの死後観に代替するものとして自然回帰という考え方が受け入れられたように思われます。
石よりも花木(明るい華やかな景観)
「脱承継」や「宗教不問」だけであれば、なにも樹木葬でなくても構いません。納骨堂や継承墓でもこうした問題をクリアにしてくれるところはたくさんあります。それでもなお樹木葬が選ばれるのは、先述の「自然回帰」志向に加えて、景観的にも石よりも花木の方が明るくて華やかだからだと思われます。
これは筆者の推測の域を出ませんが、姿かたちはそれを志向する人の内面性が表されていると言われています。
何百年何千年と同じ場所にい続けられる石は昔から永遠性の象徴として考えられてきました。墓石を志向する人は、先祖や両親から子や孫へとつながっていく「生命の連続性」を大事に考えているのだと思われます。
一方で、花などの植物は、きれいに咲き誇るもののやがては枯れて朽ちていく、刹那的なものです。樹木葬を志向する人は、いわゆる個人主義、自由な生き方を大切にする考えを表しています。
人が何に対して美的感覚や親近感を抱くか、これは個人差があるのでひと言で言い表せません。しかし、社会全体として樹木葬が広まっているのは、それだけお花のように、明るく華やかであることを求め、やがては枯れて朽ちていくという刹那的な人生観や死生観が投影されていると言えるのかもしれません。
樹木葬の注意点
1999年に祥雲寺が樹木葬墓地を開設してからまもなく24年です。時間の経過とともに、樹木葬も広く社会に認知されてきました。また、社会状況の変化に伴い、弔い全般のかたちも変化し続けています。樹木葬の注意点や樹木葬の抱える問題点について押さえておきましょう。
物足りなさを感じる人もいる
伝統的な継承墓へのお参りに慣れている人の場合、樹木葬へのお参りに物足りなさを感じることがあるかもしれません。
墓石の拭き掃除や雑草抜きは負担だという声をよく聞きますが、しかしお墓参りの醍醐味はお墓掃除だと感じている人も少なくありません。お墓をきれいにすることで、自身の心もスッキリするという効果があります。
また、樹木葬の場合、火事予防の観点からローソクや線香を使えない霊園もあります。
このように、これまで当たり前だと感じていたお参りができなくなってしまうことに、物足りなさを感じてしまうかもしれません。
返骨してもらえないこともある
樹木葬の場合は、遺骨を骨壺から出して埋葬するケースが多く、布に納めるか、あるいは木製の骨壺に移し直すか、いずれにせよ、土に還る有機素材のものを用いて埋葬します。
遺骨が自然に還ることをよしとする反面、遺骨を長く大切に保管しておきたいと考える人もいます。日本の伝統的な埋葬は、古代中国から続く埋葬の考え方を深く踏襲しており、お骨を大切にする文化が根強くあります。
樹木葬では、遺骨を土に還すことを前提としています。もしも将来的に遺骨を返却してもらいたいと思っても、物理的に困難になると思われるので、実施の際は予めしっかりと検討しましょう。
一般墓より費用が高くなることもある
「墓石=高い、樹木葬=安い」というイメージを持つ人が多くいますが、必ずしもそうではありません。
最近ではコンパクトな墓石も作られるようになり、樹木葬の費用相場よりも安価な墓石もたくさん売り出されています。
費用を安く抑えたいから樹木葬にすると考えるのは短絡的です。もしも費用をベースにお墓探しをするのであれば、樹木葬だけでなく、納骨堂やコンパクトな墓石など、幅広い選択肢の中から検討するように心がけましょう。
自分にピッタリなお墓探しには、経済産業省の認可団体である全国石製品協同組合(全石協)が運営するお墓総合ポータルサイト『みんなのお墓』 がおススメです。希望のエリアからあなたにピッタリな継承墓、納骨堂、樹木葬をご紹介いたします。
雨風や災害に弱い
どんなに強い雨が降り、激しい風が吹いたとしても、墓石であればびくともせずにそこにい続けられます。しかし樹木葬の花木はこうした雨風や自然災害に弱いという特徴があり、故人を偲ぶための墓標としては心もとない側面があります。
また、自然の花木ですから、季節によって異なる顔を見せます。契約時は満開だったお花も、実際に違う季節にお参りをしてみると、思っていたのと違う雰囲気になってしまうこともあるでしょう。
必要のない墓じまいをしてしまう
ここ最近のトレンドに流されて、まだまだ継承墓を守り続けられるのに、墓じまいをし、樹木葬を購入しようとする人も少なからずいます。
墓じまいや樹木葬の購入にもそれなりの出費がもたらされます。すでにお墓があるのであれば、余計な出費もいりませんし、家族や先祖のつながりを感じながらお墓参りができます。
どんなに個人化が進む社会だとは言え、家族や親戚、さらにはそのルーツであるご先祖さまとのつながりを大切にしている人は数多くいます。東日本大震災のあとに「絆」という言葉が流行したことがそれを物語っています。
「みんなが墓じまいをしているから」「樹木葬が人気だから」と言って、それが本当に自分たちにとって必要なのか、あるべきお墓のかたちなのか、冷静に考えてみることから始めるのもよいかも知れません。
まとめ
樹木葬が注目されている社会的背景、その理由、そして注意点について解説してきました。お墓のこと、樹木葬のことで分からないことがありましたら、どうぞ経済産業省の認可団体である全国石製品協同組合(全石協)にご相談下さい。全国47都道府県の石材会社や関連会社が力をあわせて、あなたの幸せなお墓ライフ、をサポートいたします。
お墓の基礎知識の関連記事
-514x303.jpg)
お参りが楽しくなる自然石型のお墓が密かなブームに

経産省認可「全石協」、墓じまい・改葬相談窓口を開設
-514x303.jpg)
実は2代目だった渋谷駅前の忠犬ハチ公像
-514x303.jpg)
自治体で「無縁遺骨」「無縁墳墓等」が急増

地震被害に便乗した悪質商法にご注意を!



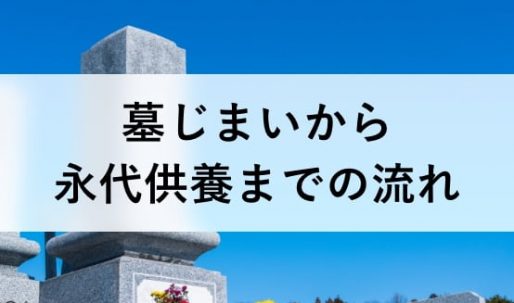
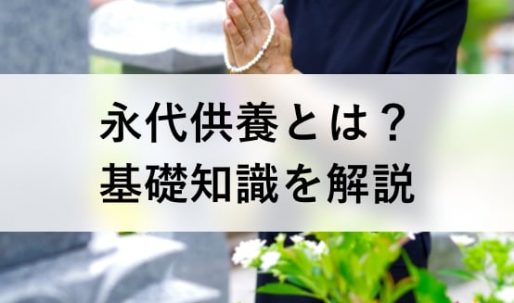
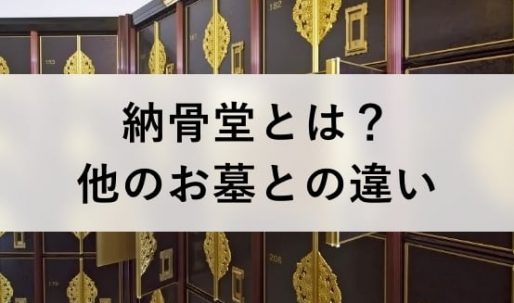
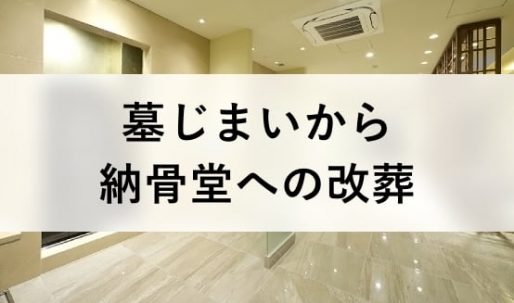
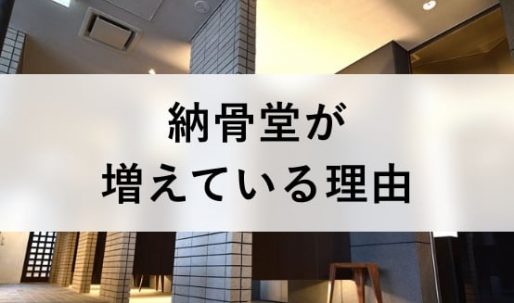
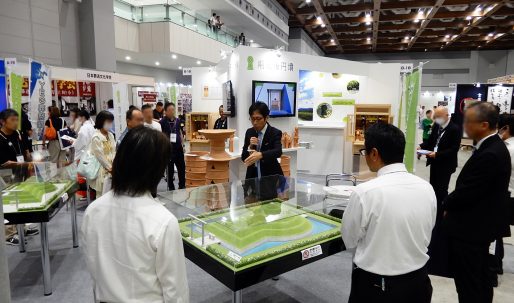
-514x303.jpg)