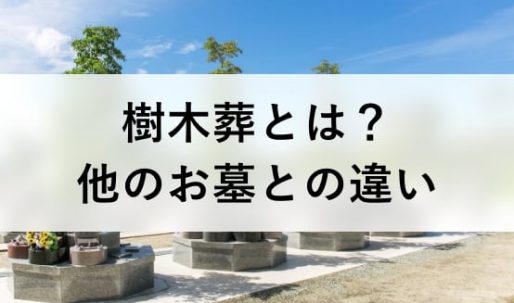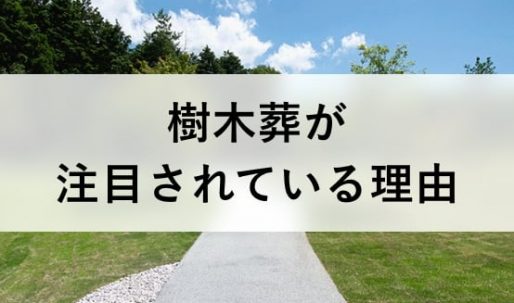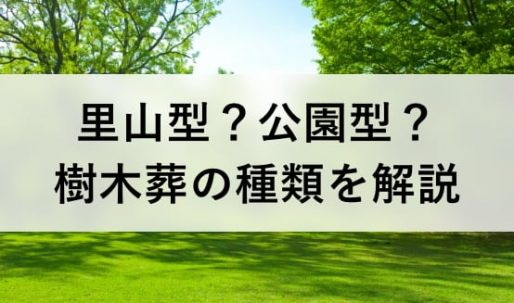2023.11.16
墓じまいから永代供養までの流れ・費用・注意点を解説
この記事の目次はこちら!
家族やご先祖さまが眠るお墓があるものの、「あととりがいない」「お墓を承継できない」などの理由で墓じまいに踏み切る人が少なくありません。その場合、墓石は石材業者に撤去してもらえるものの、中にある遺骨まで処分というわけにはいきません。遺骨はしかるべき場所に移さなければならず、そのうちの選択肢のひとつとして、永代供養という方法があります。
普段仏事や供養になじみのない方の中には、墓じまいや永代供養の意味がよく分からなかったり、意味を混同している人も少なくありません。
この記事を読んで頂くことで、墓じまいと永代供養の意味についてよく理解できます。墓じまいから永代供養するまでの流れ、全体にかかる費用、実施する際の注意点についても丁寧に解説して参ります。どうぞ最後まで読み進めてみて下さい。
墓じまいと永代供養の違い
まずは、墓じまいと永代供養の意味について押さえておきましょう。
墓じまいとは
墓じまいとはそのことばの通り、家族や先祖から受け継いだ継承墓を解体撤去した上で、遺骨を改葬(別の場所に移す)することです。
墓じまいと聞くと「墓石をきれいに片づければいいんだ」とだけ考えがちですが、実際には継承墓の中にはお骨が納められていることがほとんどですから、遺骨を別の場所に改葬し、きちんと供養をして差し上げるところまでが墓じまいです。
遺骨の改葬先としては、新たに購入した墓石、納骨堂、樹木葬などが挙げられます。また、さまざまな事情で個別のお墓を持つことをせず、他の方と同じ場所に埋葬する合祀墓にお骨を納めて、永代供養にする人もいらっしゃいます。
永代供養とは
永代供養とは、遺骨を寺院や霊園に預けて、家族の代わりに永代にわたって供養してもらうことです。
本来、供養とは自分たちが亡き両親、祖父母、ご先祖さまに対して行うものですが、子や孫がいない世帯や、単身者の世帯では、継承墓を守っていくことは困難です。
そうした方々の最後の受け皿として永代供養があります。お寺は世代を超えて存在し続ける場所ですし、日本の仏教各派は1000年近い歴史を紡いできた実績があります。こうしたお寺という場所や僧侶という存在の「長く続くことの安心感」があるからこそ、死後の供養を任せることができるのです。
墓じまいや永代供養が増えている理由
墓じまいや永代供養が増えていると言われていますが、そこには次のような社会的背景があります。
- 家族やあととりがいない
- お墓が遠方にある
- 納骨堂や樹木葬人気の上昇
家族やあととりがいない
少子高齢化により、日本の人口は減少傾向にあります。親世代よりも子や孫の世代の方が少なくなる以上、一家にひとつの継承墓を維持することは困難にならざるを得ません。
「家族がいない」「あととりがいない」「娘しかおらずみんな嫁いでしまった」などの理由から、これ以上継承墓を守ることができない人が、墓じまいをして永代供養に踏み切るケースが見られます。
お墓が遠方にある
多様なライフスタイルによって、故郷を離れて暮らすのが当たり前の時代です。そのため、故郷にあるお墓へのお参りがなかなかできず、お墓が荒れてしまうことに胸を痛める人も少なくありません。
こうした人たちの中には、故郷のお墓をきれいに片づけて、自分たちの住んでいる場所の近くに新たにお墓(納骨堂や樹木葬なども含む)を構える人もいます。
納骨堂や樹木葬人気の上昇
伝統的な継承墓よりも、より現代のライフスタイルにマッチした納骨堂や樹木葬が選ばれている傾向にあります。また最近では、墓石においてもコンパクトで承継不要のものが選ばれています。
これらの大きな特徴は、墓じまいの心配がないこと。墓石を解体撤去するにはさまざまな手間、大がかりな工事、それに伴う費用がかかりますが、納骨堂の場合、不要となれば中の遺骨を取り出して区画を明け渡すだけで済みますし、樹木葬の解体撤去は墓石のそれと比べるとはるかに安価なコストで済みます。
そのため、最近売り出されている納骨堂や樹木葬、場合によっては墓石でさえ、将来的な墓じまいや永代供養を保証したものが多く、こうした安心感が、元気なうちに墓じまいをする人が多い理由の一つと言えるでしょう。
墓じまいから永代供養への流れ
- 永代供養を依頼する寺院や霊園を探す
- 墓地の管理人に墓じまいの意向を伝える
- 墓じまいを依頼する石材店を探す
- 改葬許可申請をする
- お性根抜きの法要をしてもらう
- 墓じまい工事の着手と遺骨の取り出し
- 永代供養墓への埋葬
それでは、実際に墓じまいから永代供養をする場合、どのような流れになるのでしょうか。施主さまの目線に立って解説いたします。
永代供養を依頼する寺院や霊園を探す
まずは、永代供養をどの寺院、霊園ですべきかを考えます。大切なご先祖さまの遺骨を預けて、自身の死後も供養を任せる先となるため、安心できるところに依頼したいものです。
すでにお寺との付き合いがある場合は、そのお寺に永代供養をお願いするのがスムーズです。もしも、別の場所で永代供養したい、あるいはこれまでお寺との付き合いがなかったのであれば、新たに永代供養先を探さなければなりません。
まずは、自身の希望する条件に適う寺院や霊園をインターネットで検索し、その後電話問い合わせまたは資料請求、直接訪問という流れが一般的です。主に次に挙げる事柄から、寺院や霊園を選ぶ人が多いようです。
- 相性や雰囲気(住職やスタッフの人柄や考え方など)
- アクセス(お墓参りのしやすさ)
- 周辺の環境(落ち着いてお墓参りできるか)
- 施設の充実度(トイレ、ゴミ箱、水場、共用通路など)
- 予算(初期費用や管理費)
- 供養の方法(埋葬や礼拝の方法、供養の期間など)
供養とは心に関わる営みです。ここで特に大切にしてほしいのは、あなたとの相性や実際に足を運んでみて感じた雰囲気です。まずは現地を訪問し、住職やスタッフと話をしてみて、自身との相性をはかってみましょう。
住職やスタッフの人柄や考え方、そして現地の雰囲気を快く受け入れられるかどうかは、永代供養を考える上でもっとも重要なポイントです。これらはネット検索や電話問い合わせだけでは感じられません。ご自身の肌で受けた感覚こそを大切にしましょう。
墓地の管理人に墓じまいの意向を伝える
永代供養先が決まったら、次にいまあるお墓を墓じまいすることを、墓地の管理者に伝えます。
公営霊園や民営霊園の場合は、管理事務所に出向いて墓地の返還手続きをします。寺院墓地の場合は住職に、共同墓地の場合は自治会長や墓地委員会などに直接伝えましょう。
墓地の使用権は管理者に返還するのが原則です。その区画が不要になったからといって、譲渡や転売などはできませんので気を付けましょう。
また、墓地区画内はきれいに整地、いわゆる更地にして返還するのが基本です。霊園によっては墓じまいの工事を行う石材店が指定されていることがありますので、あわせて管理者に確認をしておきます。
墓じまいを依頼する石材店を探す
墓石の解体撤去工事をする石材店を探します。前述した通り、もしも指定石材店がある場合は、そちらに依頼します。
指定石材店がない場合は、施主が石材店を探します。実際に現地に行ってもらい、見積もりをしてもらいましょう。一社ではなく複数の石材店から相見積もりをとることで、より安く、より安心できる石材店と巡り合えるでしょう。
しかし、ひとつのエリアの中にもたくさんの石材店があり、まずどこから問い合わすべきか分からないものです。そんな時こそ、経済産業省の認可団体である全国石製品協同組合(全石協)が監修する日本最大級のお墓総合ポータルサイト『みんなのお墓』がおススメです。あなたの希望するエリアの優良石材店をすぐに検索できます。
改葬許可申請をする
永代供養先が決まり、墓じまいの段取りが整うと、遺骨を別の場所に移す「改葬」の許可を、改葬元の自治体に申請しなければなりません。
改葬許可の申請から、改葬の実施までは、次のような流れを踏みます。
- 改葬元の自治体が定める「改葬許可申請書」に必要事項を記入します。この時、納骨の事実を証明してもらうために、改葬元の墓地の管理者に署名と捺印をもらいます。
- 改葬先のお寺(永代供養をしてくれるお寺)から、「受入証明書」を発行してもらいます。
- 改葬元の自治体に(1)と(2)を提出し、内容に不備がなければ、役所から「改葬許可証」が発行されます。
- 改葬元の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬先の墓地管理者に「改葬許可証」を預け、遺骨を納めます。
お性根抜きの法要をしてもらう
石材店に墓じまいの作業をしてもらう前に、必ずお寺を墓前に招いて、お性根抜きの法要をしてもらいます。お性根抜きは「閉眼(へいがん)供養」「撥遣(はっけん)供養」「御霊抜き」などとも呼ばれます。
お性根抜きがされていないと、石材店は墓じまいの工事にかかってくれないことがほとんどです。それは、墓石の中に仏さまが込められているだけでなく、長い年月をかけて手を合わせてきた先祖代々の想いや念が込められているからです。
そう考えると、お性根抜きとは単なる儀式にとどまらず、これまでご先祖様の遺骨を守ってきてくれた墓石に対する感謝を表明する供養だとも言えます。モノにも魂が込められていると信じる日本人の宗教観が如実に表れていると言えるでしょう。
墓じまい工事の着手と遺骨の取り出し
墓じまいの工事そのものは、石材店に一任します。石塔を解体し、中から遺骨を取り出します。そして土台となる石や基礎も解体し、更地化していきます。
墓じまいにかかる日数は墓地の広さや状況によって異なります。1日で終わることもあれば、数日にまたがって行われることもあります。
遺骨の取り出しは、施主が立ち会うのが理想ですが、どうしても現場に足を運べない時は石材店に取り出してもらい、一時的に預かっておいてもらいましょう。また、墓石の状況によっては、お性根抜きの法要の時に、遺骨の取り出しを行うこともあります。
取り出した遺骨の状態は、実にさまざまです。骨壺の中にきれいに納まっているケースもあれば、遺骨と土が混ざっているケースも少なくありません。遺骨の取り扱いについては永代供養をしてくれるお寺や霊園に確認し、対応します。骨壺に入れた状態のままでよいか、事前に洗骨しておかなければならないなど、何らかの指示があるものと思われます。
永代供養合祀墓への埋葬
新たに永代供養をしてくれるお寺や霊園に遺骨を持参して、永代供養合祀墓に埋葬します。埋葬の際には、僧侶による読経供養が行われます。
遺骨をどのように供養するかは、永代供養のプランによって異なります。遺骨を預けた時点で合祀にするのか、あるいは一定期間は骨壺のまま保管するのか、保管場所は永代供養墓、納骨堂、樹木葬などさまざまな方法があります。
墓じまいと永代供養にかかる費用
墓じまいから永代供養をするには、お寺、霊園、役所、石材店など、さまざまな方面への対応が求められ、それぞれに費用がかかります。この章では、具体的にどれくらいの費用がかかるのかを個別にご紹介いたします。
永代供養の費用
永代供養にもさまざまな種類、方法があります。それは、遺骨をどのような形で預かるか、どのような形で供養をしてもらうか、などによって異なります。
ここでは主に、永代供養の種類別に、それぞれの費用を解説いたします。
永代供養墓 50万円~200万円

形状はさまざまですが、従来型の継承墓よりはコンパクトなものが多く、モダン型、プレート型などがあり、それらによって費用に幅があります。また、多くの霊園やお寺では、石碑の費用と永代供養の費用を合わせてセットプランとしています。
期限付き墓石 30万円~200万円

また、お墓の中の遺骨は、墓石の撤去とともに合祀墓に移されて永代供養してもらえます。
費用に大きな幅があるのは、永代供養墓と同じで、墓石の形状や納骨できる人数などによって異なるからです。
合祀墓 5万円~30万円

形状はさまざまですが、はじめから土の中に合祀するもの、一定期間骨壺のまま保管できるよう躯体の内部に棚を設えているものなどがあります。なお、後者の場合も最終的には土の中に埋葬できるよう設計されています。
この合祀墓は寺院や霊園が準備するものであり、施主がお墓を出して自ら建立する必要がありません。その分、費用は安く抑えることが可能です。
5万円~30万円という費用の幅は、主に供養の方法によって差があります。遺骨を埋葬するだけであれば安価に済みますが、数年間は土に還さずに骨壺のまま保管してもらう、戒名を頂く、一定期間は個別に供養してもらう、などの手厚い供養を望むのであれば、高額になっていきます。
納骨堂(20万円~200万円)

納骨堂の中には「納骨壇」と呼ばれるものが並び、この中に遺骨を納めます。省スペースで比較的安価な「ロッカー型」、1列を1つの家族で使用できる「仏壇型」などがあります。
また中には、屋内に石のお墓が並ぶ「石碑型」や、建物全体がコンピューター制御されており、お参りの際に遺骨がバックヤードから流れてくる「自動搬送型」と呼ばれるものもあります。こうした形状やシステムの違いにより、費用も大きく変動します。
また、納骨堂にも永代使用のものと期限付きのものがあり、これらも費用に影響します。期限付きプランを選んだ場合は、契約期間が終了後、遺骨は合祀墓に埋葬されるのが基本です。
公園型樹木葬(40万円~150万円)

樹木葬とは、あくまで樹木を墓標としたお墓のことですが、最近では石材を用いた樹木葬も少なくなく、デザインや仕様、納骨できるお骨の数などによって費用が変動します。
墓地の返還に伴う費用
墓じまいをするにあたり、これまで自分たちが使用していた区画は霊園に返還しなければなりません。墓地の返還に伴う費用は、基本的には不要です。
ただし寺院墓地の場合で、墓じまいがそのまま離檀(檀家関係を解消すること)になる場合は、「離檀料」が必要となる可能性があります。
離檀料とは、あくまでもお寺に納められるお布施の一種ですから、本来定額がありませんし、お寺によっては離檀料を受け取らないところもあります。とはいえ、これまでご先祖様がお世話になったお寺ですから、感謝を込めて離檀料を包むことは、お寺に対してとても丁寧な対応だと言えるでしょう。
一部マスコミなどで、離檀料に関するトラブルを見聞きしますが、基本的にお布施の金額は受け取る側ではなく、納める側が決めるものです。もしも法外な離檀料の請求が不当だと思われるようであれば、弁護士や、その宗派の本山寺院などに問い合わせてみるなどの方法があります。
改葬許可を行政書士に代行依頼した場合の費用
改葬元の自治体への改葬許可申請は、家族が行うのであれば特別な費用はかかりません。また、手続きの内容もそんなにむずかしくはなく、多くの場合、家族ご自身が手続きを行っています。
しかし、「時間がなくて忙しい」「煩雑な手続きが苦手」「改葬すべき遺骨の数が多くて大変」などの理由から、行政書士に手続きを代行してもらう人も少なからずいます。この場合、手続き代行の報酬を行政書士に支払わなければなりません。
報酬は遺骨の数によって異なりますが、手続き代行のみであれば、5万円〜10万円が相場でしょう。中には永代供養先や石材店のあっせんなど、墓じまい全体をサポートしているところもあるので、費用の中に何が含まれているかはきちんと確認しておきましょう。
お性根抜きにかかるお布施の費用
お性根抜きのお布施の費用相場は1万円~5万円です。お寺や地域によって費用が異なることがある上、墓じまいするお墓の数によって変わることもあります。
石材店への費用
墓石の解体撤去工事をしてくれる石材店への費用は、墓じまいする墓石の数、墓地の面積、墓地の状況などによって大きく変動します。
具体的には、墓石だけでなく土台となる石や基礎の解体撤去、残土の処分、区画の整地化、さらには解体した石材を運搬して、粉砕処分しなければなりません。
また、作業しやすい墓地であればいいのですが、狭くて重機が入らない、坂の勾配が急など、墓地の環境も、費用の変動要因のひとつです。
一般的な相場は墓地面積1㎡(1m×1m)で20万円~30万円だと言われていますが、まずは石材店に現地を見てもらい、見積もりしてもらいましょう。どの石材店に相談すべきか分からない方は、『みんなのお墓』を運営している全国石製品協同組合(全石協)にご連絡下さい。信頼できる石材店をご紹介いたします(一部地域を除く)。
墓じまいと永代供養の注意点
ここまで、墓じまいをして永代供養にするまでの流れを解説しましたが、最後に、あなたの墓じまいや永代供養が後悔のないものとなるよう、注意点をお伝えしておきます。
墓じまい=永代供養ではない
墓じまいをしたからと言って、必ず永代供養にしなければならないわけではありません。自分たちの住む近くにコンパクトなお墓を構えることもできますし、合祀以外にも、コンパクトな墓石、納骨堂、樹木葬などのさまざまな選択肢があります。世の中のトレンドに左右されずに、自分たち家族にとってもっとも納得できる形を考えてみるのもよいでしょう。
大切な親戚や関係者には事前に連絡・相談を
お墓は、家族だけでなく、そこに眠る故人さまやご先祖さまとご縁を紡いできた人たちがお参りできる場所でもあります。自分たちだけで判断するのではなく、大切な親戚や関係者には、事前に連絡や相談をして、こちらの想いを伝えておきましょう。
菩提寺がある場合はしっかりこちらの想いを伝える
長らくご先祖さまの供養をしてくれていた菩提寺には、どうして墓じまいや永代供養をしなければならないか、こちら側の事情や想いをきちんと伝えておきましょう。
墓じまいはバチあたりではない
墓じまいそのものは、決してバチ当たりではありません。両親やご先祖様が守ってきたお墓を自らの手で片づけることに後ろめたさを感じる人もいることでしょう。
しかし、「やがて承継者がなくなるのであれば、自らの手でお墓をきれいに片づけて、お骨をしかるべき場所に移し、きちんと供養しよう」と考え、実践することは、それだけご先祖様のことを大切に考えていることに他なりません。
これまでお世話になったお墓に、感謝と敬意を持つことで、きっとお墓も、そしてご先祖さまも納得して下さるはずです。
まとめ
お墓の基礎知識の関連記事
-514x303.jpg)
お参りが楽しくなる自然石型のお墓が密かなブームに

経産省認可「全石協」、墓じまい・改葬相談窓口を開設
-514x303.jpg)
実は2代目だった渋谷駅前の忠犬ハチ公像
-514x303.jpg)
自治体で「無縁遺骨」「無縁墳墓等」が急増

地震被害に便乗した悪質商法にご注意を!

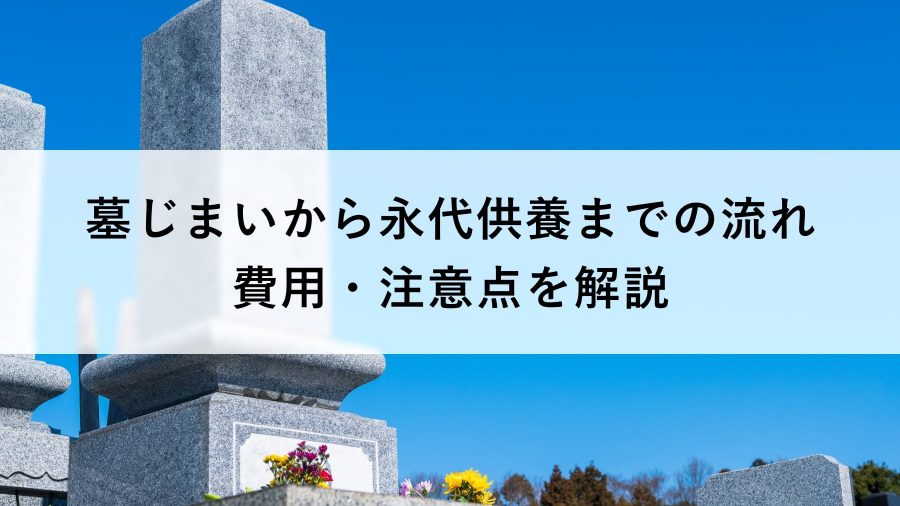

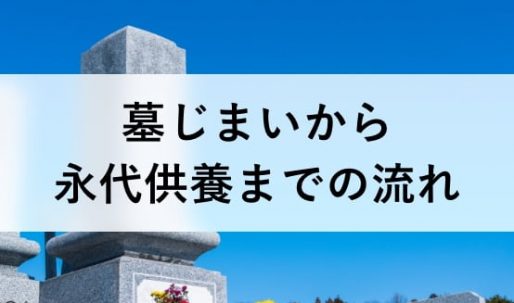
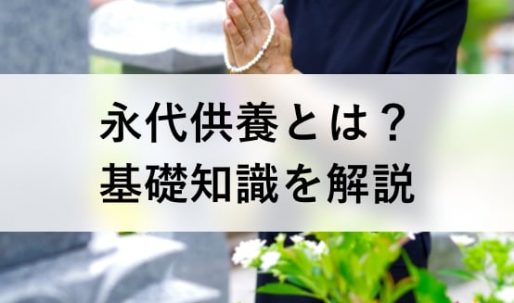
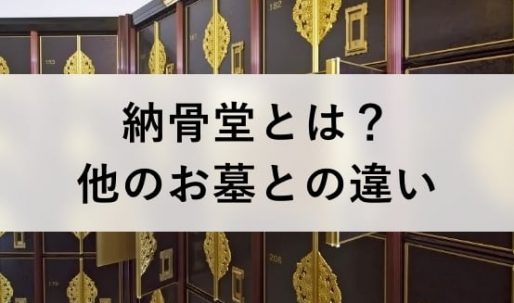
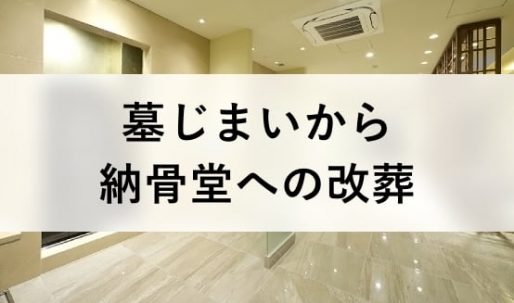
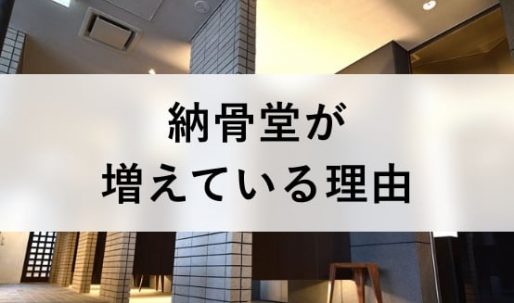
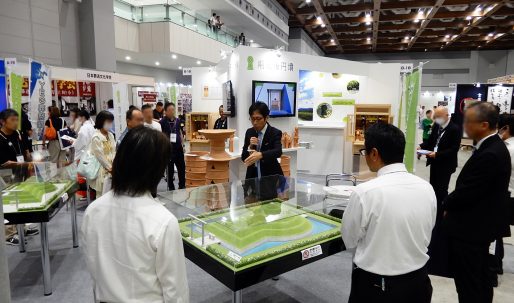
-514x303.jpg)